2024/6/24月曜日
5時に起床し洗濯と朝食作り。
6時45分に畑へ。
まずは先週種を撒いた箇所の発芽チェック。
不織布をひっくり返すと、その不織布自体が緑色、と言うね。
やられた感満載。

発芽してる所はほんの数カ所。
殆ど発芽せず。
捲ってみると、緑色の液体がべっとり。

もう少し様子見て、発芽しないようならバックアップ用の苗を植える事に。
そして、竹酢液を掛けながら他の畝もチェック。
畝の外に撒かれた跡が。

行動パターンとして、雨に便乗して撒く。
だから、通常、雨上がりの作物て生き生きとしているのに、うちのは枯れてたり病気になってたり↑の枝豆のように虫が付いてたり。
この中で、悪魔くんによる行動は枝豆の葉を食べていたイモムシだけ。
他の枝豆見たけど、ここにあるのだけイモムシが居た。
悪魔くんは、嫌がらせするにしても、ワンポイントギャグをかます。
緑色の悪い液体撒くだけては芸が無い。
畑の数カ所に溜池のように溜まった水をスコップによる土木工事で排水。
気が付くと9時に。
買い物をしてから帰宅。
帰宅後も病人の洗濯物の追加等でやる事満載。
気が付くと12時に。
夫にパスタを茹でトマトスープパスタを用意したら、洗濯物干し等が13時まで続き、疲労困憊。
食事はパスした。
午後は調べ物。
夫からアメリカがロシアの海岸で休暇中の民間人にクラスター爆弾を落とした、と聞いた。
世の中、可怪しいな。
その裏を取っていたら、一応、Xでビーチで破裂音に人々が逃げ惑う動画やラブロフ外相等が遺憾の意を表明していいる記事は見つけた。
幼児を含む3名が亡くなった、とあった。
日本の大手メディアは報道したのだろうか。
その後、中室勝郎著「漆の里・輪島」の読書をスタート。
何故、国は能登半島地震で被害に遭った人々を救済しないのか知りたくなった。
何か因縁あるの?
その過程で輪島市内の神社の騒動で一農民が磔に遭った事件を知り、少し調べた。
その該当神社について調べているうちに、偶然、まだ通行止めの箇所が多数あるのを知った。
は?
もう、半年経つけど?
その、通行止めと通行止めの間の孤立集落の人々はどのように生活しているのか?
それを調べても情報は無かった。
の時には有り得なかったかと。
この違いは何?
税金取るだけ取ってこんな時に何もしないなら国要らんわ。
何もしてくれないなら所得税無しに住民税(年貢)だけにして地方自治しようぜ。
藩政時代に戻ろう。
17時半から夕食作り。

モズクと新生姜の温豆腐、トマトスープ、バルサミコ酢サラダ、ウォッカ梅酒ロック。
病み上がり連中からのリクエストで爽やかメニュー。
自分は昨日の昼以来の食事なので何を食べても美味しかった。
お皿を洗ったら営業終了。
昨日の文永の役の本題に入りたいと思う。
遂に、クビライより7月に日本遠征するよう下達。
兵員一万5千人。
後に追加で2万6千人に倍増。
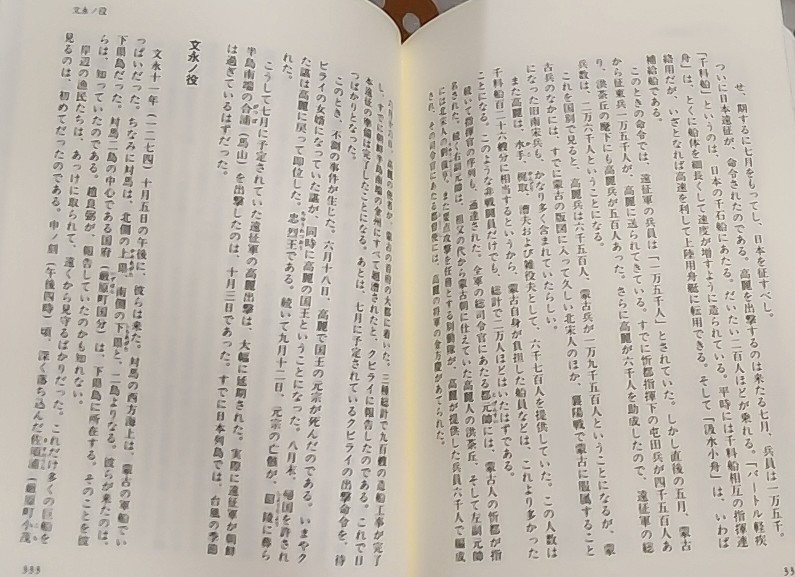
都元帥(総司令官)蒙古人忻都
右副元帥: 高麗人洪茶丘
左副元帥:北宋人劉復亨
高麗兵六千人の別働隊都督使(司令官)高麗人 金方慶
6/18, 高麗の国王元宗が薨去。
7月に予定されていた遠征は10/3まで延びた。
既に日本は台風シーズンに。
文永11年(1274年)10/5の午後4時、対馬の下県島佐須浦(小茂田浜)に襲来。
次々接岸しては上陸し始めた。
漁民が宗資国に急報したのは午後6時。
掻き集めた軍兵80騎で炬火で山道を照らしながら中央部の鶴翼山を越えての難行軍。
厳原から小茂田浜までドライブしたけど結構時間掛かった。
夜が明ける直前佐須浦に到着。
海岸には既に1千人を超える蒙古勢が上陸。
80人対1千人。
こんな絶望的な戦いある?
が、これは武士はやらなければならないんよ。
島民が山の中に隠れる時間を稼ぐ為に。
資国は朝鮮語のわかる真継を使者として蒙古軍に送った。
が、蒙古勢は真継に矢を射掛けて来た。
資国は真継を呼び返し、下知を発し応急の陣を構えこちらからも矢を射返した。
斉藤兵衛三郎資定の矢は10人以上射倒した。
2時間は持ち堪えたが戦死した者として12名が伝わっている。
対馬の守護代兼地頭の宗資国、兄の右衛門三郎盛継、資国次男右馬次郎、猶子弥次郎などの宗一族の他、資国郎等の荘ノ太郎入道、流人の江井藤三、対馬御家人の斉藤資定などである。
宗資国は戦死前に小太郎・兵衛次郎に博多に知らせに行くよう命じている。
博多に着いたのは7日目の10/13。
連絡を受けた少弐資能は鎌倉へ飛脚便。
勝本港と湯本浦に接岸。
蒙古勢400に対し麾下100騎で陣を布いた。
両軍の矢頃(射程距離)の差は大きかった。
日本軍が一町弱(約100m)でしかない、て十分凄いやないかー!
これに対し日本の半弓程の小振りな蒙古兵の弓は二町もの遠くから矢の雨を降らせた。
半世紀に及ぶ泰平で鎌倉武士も腕が落ちた。
景隆軍は樋詰城に追い込まれそこで自刃。死の直前、景隆は下人の宗三郎を脱出させ博多に派遣。
肥前国石志領主石志源三郎兼は自身と嫡子二郎は戦死を覚悟で出陣するので、10/16, 娘の猟子に対し自領の譲状を書いている。同じ様な覚悟をした鎮西武士が相次いで博多に集結。
大宰少弐の武藤資能は77歳。
流石に高齢なので全軍の指揮は40代の長男・少弐経資へ。
他にも、有馬、大村、臼杵、高木、竹崎、戸次、山鹿、龍造寺、松浦党、児玉党。
余りの大人数が集結した為、手柄を立てる根拠の相手方の首(兵)の数が足りないのでは、と危惧する者も居た。
1185年の源平合戦壇ノ浦の戦いでは源氏840艘平氏500艘。
全て小船。
1274年の弘安の役では船の数は900艘だがどれも大型船。
90年経ち船は大型化。
博多湾が陸地に変化した、と言うのも頷ける。
10/19に博多湾に現われた蒙古軍はその日は船から炊煙を上げ腹ごしらえ。
腹が減っては戦はできぬ、からね。
そして、翌10/20, 遂に100艘程の軍船が真っ向から筥崎(はこざき)八幡宮目指した。約二万の蒙古兵だ。
この時少弐景資の子資時は12歳の初陣。「ヤァヤァ我こそは、俵藤太と異名をとりし藤原秀郷から十一代の孫武藤景資の子資時なり。当年取って12歳。今日こそ初陣なり。ならばこの矢を受けてみよ」と可憐な声で名乗りを上げた。
先祖からの系図を読み上げた「氏文読み」が済むと古式ゆかしく鏑矢を蒙古兵の頭上目掛けて放った。
ブーンと音を発して矢は彼方に飛んだ。
日本人にとっては極めて優雅な振る舞いだったから全軍が固唾を飲む想いだった。
しかーし、蒙古兵には日本語も通じなければ鎌倉武士の作法も知らない。
「何ごとならん?」と寸時の間呆気に取られて見ていたが鏑矢が奇妙な音を発して頭上を飛び去ると一斉に笑い出し、次の瞬間銅鑼を叩いて攻撃に出た。
※開戦劈頭に射る矢は敵に命中させてはいけない事に成っている。
蒙古兵はそれを知らなかった。
蒙古兵と鎌倉武士では風俗習慣から戦い方に至るまで違いが大きかった。
鎌倉武士では
①一騎打ちが当然。複数で敵一騎と戦うのは卑怯な振舞い。
②最初に敵味方双方が名乗り合うのも当然の礼儀、リスペクトよ。
③騎馬武者が徒武者を攻めるのは最も卑怯。
④徒武者が騎馬武者に戦いを挑むのは勇敢な事と賞賛された。徒武者に攻められた騎馬武者はその場を去らねば成らなかった。勝っても卑怯と謗られ負けたら死ぬだけだったから。
⑤徒武者が騎馬武者と戦うにも一定の作法があった。大切なのは敵の馬の足を薙いではいけない。
⑥敵の首を取る。論功行賞に備えてもだし敵手に対する敬意からでもあった。
これに対し蒙古兵は、
①名乗りも聞かず集団戦法を取った。「ヤァヤァ我こそは〜」と名乗っている間に十数人にすっかり包囲されている事も度々あったそうだ。
②また、蒙古兵の多くは徒武者だった。背後に騎馬の将校が居て銅鐸や太鼓を打ち鳴らして、包囲、攻撃、或いは退却などを指揮したのである。
③日本の騎馬武者の多くは蒙古側の騎馬兵に突き進むと蒙古側の歩兵に足下から長槍で突き上げられた。鎌倉武士にまだ槍は無かった。また、毒矢を使う事も思いつかなかった。矢傷から全身に毒が回って落馬すると蒙古兵多数が寄り重なって殺された。
④最も手を焼いたのは「てつはう(鉄砲)」大きな鉄丸に火薬を詰めたものでこれに点火して投げると爆発。直接的な殺傷効果は乏しかったが爆発した時に発する轟音は鎌倉武士を驚かせただけでなく乗馬を驚かせ竿立ちさせ背の武士を落馬させた。落馬した途端に蒙古兵多数の餌食である。
豊後国日田郷領主日田永基は乗馬が特別に悍馬だったので麾下の郎等300騎を置き去りにして敵中に突撃。馬だけが戻って来た。松浦党の肥前国松浦西荘佐志村の領主佐志房は息子の直、留、勇の3人と共に戦死を遂げた。
少弐景資もたまたま一騎だけになった所を数十人の一団に狙われた。景資の乗馬は逸物だった為一鞭当てて馳せ過ぎざま背後を振り返って一矢を放つと先頭の巨漢に命中。身の丈7尺の巨漢は落馬。捕らえた蒙古捕虜に聞くと左副元帥の劉復亭だった。死にはしなかった。
↑この事から筥崎八幡宮近くに上陸したのは北宋出身の中国人。日本軍は劣勢で八幡宮も焼け落ちた。
蒙古軍は左翼は左副元帥の劉復亭、右翼は右副元帥の洪茶丘、中央部は都督使金方慶指揮の高麗勢が担当。
総指揮官の蒙古人忻都直率の蒙古兵は安全な軍船で勢力を温存。
日本軍は敗色濃厚。
右翼の洪茶丘勢が今津から赤坂まで進撃!軽装軽快な蒙古兵に比べ日本軍の大鎧は兎に角重かった。
慣れない外人との戦いというのもあら日本軍の疲労は甚だしかった。
何より1185年から約90年間泰平の世が続き鎌倉武士の戦闘能力も低下していた。
成る程、1945年の第二次世界大戦から90年後がDSのパターンて事か。戦の記憶のある人々が皆死ぬ頃。
パンデミックは100年だけど。
午前8〜10時に開戦し只管戦い続け、夕暮れになると東南方面那珂川上流の太宰府に向かって退却。
博多湾と太宰府の間に横たわるのが長さ1kmの水城。
これは嘗て天智天皇が664年に唐・新羅連合軍の攻撃に備え造らせた土塁。
基底部の幅は37m。
高さは14mある。
2箇所に城門が設置されているが元々は水を溜めていたらしい。日本軍はここに立て篭もり太宰府を守る事に。

http://www9.plala.or.jp/kinomuku/dazaifu/mizuki.html
勝ちに勝った蒙古軍は突如軍船へ引き揚げた。
水城の前が泥地になっていたからではないか、とも言われている。
その夜博多湾を強風雨が襲った。蒙古の軍船の多くは難破し岸辺に乗り上げて木っ端微塵に。戦死及び溺死は一万三千五百人。総勢四万六千人の三割が死亡。DS親玉大喜びや。忻都、洪茶丘、劉復亭、金方慶は助かって無事帰国。
蒙古の軍船は同型艦を並べて鎖で結び付け甲板に板を並べて各船間の往来を自由に。
静波なら問題無いが荒波の場合船腹と船縁が衝突しまくる。しかも、時期的に陰暦の10/20は陽暦の11/19日。
冬やん。
冬の玄界灘のよくある強風で破壊されたから船の造りが脆かったとしか。
明くる21日の朝、蒙古の船1艘も無き、とある。
蒙古側にしてみればただの威力偵察だったのでは、と著者も推察。
兵士の数は僅か二万六千人だった。
10/6対馬失陥の報は10/17に京都へ、10/14に壱岐島占領は10/28に京都へもたらされた。
今日はここまで。
本日も引用は奥富敬之著「時頼と時宗」
最高立った。
今日はここまで。
歩数計は8451。
充実した一日だったー。